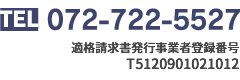アップルが「iPhone14」発表、カメラ性能向上-米国で値上げなし (2)
アップルは今年、大型ハイテク株で最優秀銘柄となっている。10億人を超すユーザーにアプリや動画、フィットネス、ゲームのサブスクリプションといったサービス購入を訴求できる能力が、投資家から評価されている。アップル株にとって次の大きな材料は10月下旬に発表される7-9月(第4四半期)決算になる。
アップル株は年初来で約8%下げているが、ナスダック100指数は約22%安。ブルームバーグのまとめによれば、アナリスト50人のうち約96%がアップル株の買い、もしくは維持を推奨。売りを勧めているのは2人にすぎない。
アップル凄いですね。欲しいですが、円安の影響を受けてかなりの金額になりそうです。ラップトップが買えるくらいの金額です。
日本市場でも9月16日から発売を開始するそうだが、日本での価格は標準機種で税込み11万9800円からと、現行モデルの前機種「13」より大幅な値上げとなるという。
きょうの各紙も「iPhone14、逆風の船出」(朝日)や「iPhone14最安12万円、日本、円安影響」(毎日)、「iPhone14逆風下の発売 物価高 市場縮小 米中対立、米国では価格据え置き」(日経)などのタイトルで、総合面や経済面で大きく報じている。
どうしようか悩みます、、、、